注文住宅では「見た目の美しさ」も大切ですが、暮らしやすさの本質は“使いやすい収納設計”にあります。収納が不足したり、動線を遮ったりする設計ミスは、住み始めてから後悔につながります。本記事では、注文住宅で後悔しないための収納設計の基本と実例を紹介します。
1. 収納の目的を明確にする
まず、「何をどのくらい収納するか」を洗い出すことがスタート。以下のような分類でチェックすると整理しやすいです:
- 日常使いのもの(衣類、食器、掃除道具など)
- 季節モノ・行事用品(コート、扇風機、クリスマス飾りなど)
- 書類・貴重品・思い出品
- 家電・予備品(掃除機、予備の照明器具、工具など)
このように分類することで「収納スペースを何畳分にすればいいか」「どこに配置すれば動線を邪魔しないか」が見えてきます。
2. 家事動線を考慮した配置
収納は“そこに置いたら使いやすいか”が鍵。
例えば:
- キッチン近くにパントリー・食品庫を配置
- 洗濯機・乾燥機近くに洗濯物用収納(下着・タオル類)を設置
- 玄関近くに靴・外出用品収納(コート掛け・傘立てなど)
- 各階ホールに共用収納を設ける(掃除道具・日用品ストックなど)
こうした“動線に沿った収納配置”は、日々の動きをスムーズにします。
3. 収納の種類と工夫ポイント
3‑1. 可動棚・可変棚を多用する
収納するモノは大きさや量が変わるので、可動棚や高さを変えられる棚で柔軟性をもたせます。将来的な整理替えや家族構成の変化にも対応できます。
3‑2. 引き出し式収納で使いやすさを向上
奥行きのある収納は、下段にしまったものが見えにくくなりがち。スライド式や引き出し式にすることで、奥のモノも取り出しやすくなります。
3‑3. オープン収納とクローズ収納のバランス
見せる収納(飾り棚など)と隠す収納(扉付き、本棚裏など)をバランスよく使うことで、デザイン性も損なわず整った印象にできます。頻繁に使うモノはオープン側、来客に見せたくないモノは扉付き側に分けると効果的です。
3‑4. 天井近くのデッドスペース活用
梁や天井高を利用して、上部に収納スペースを設けると収納量を補えます。軽いモノや使用頻度の低いモノに向いています。
4. 実例紹介:成功例と失敗例から学ぶ
成功例:回遊動線+各所収納の融合
ある住宅では、キッチン → パントリー → サブ収納 → 玄関への回遊ルートを設け、そこに小さなストック棚や掃除道具収納を点在させました。これにより、買い物帰りや掃除の際の導線がスムーズになりました。
失敗例:収納を量優先で配置した結果、通路が狭くなる
収納容量だけを重視して壁際に大きなクローゼットを設けたものの、扉の開閉や通行スペースが狭く、家具の配置や生活動線に支障をきたすケースもあります。
5. コストとのバランスを意識する
収納を充実させるほどコストもかかるため、優先順位をつけることが大切です。
- 使い勝手を重視すべき収納(キッチン・洗面・玄関)はしっかり確保
- 飾り棚やオープン収納はコストを抑えても代替案あり
- 造作家具と既製家具を組み合わせてコスト調整
- 将来リフォームで拡張できるよう配線や補強を想定しておく
まとめ:収納設計で暮らしやすさをつくる
収納は単なる「隠すスペース」ではなく、生活動線に沿った「仕組み」です。注文住宅設計の際は、収納の目的を洗い出し、動線を意識した配置、使いやすい仕様、コスト管理を意識してバランスよく設計することが大切です。今日紹介したポイントをもとに、あなたの家づくりに合った収納プランを考えてみてください。


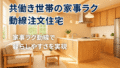
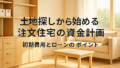
コメント